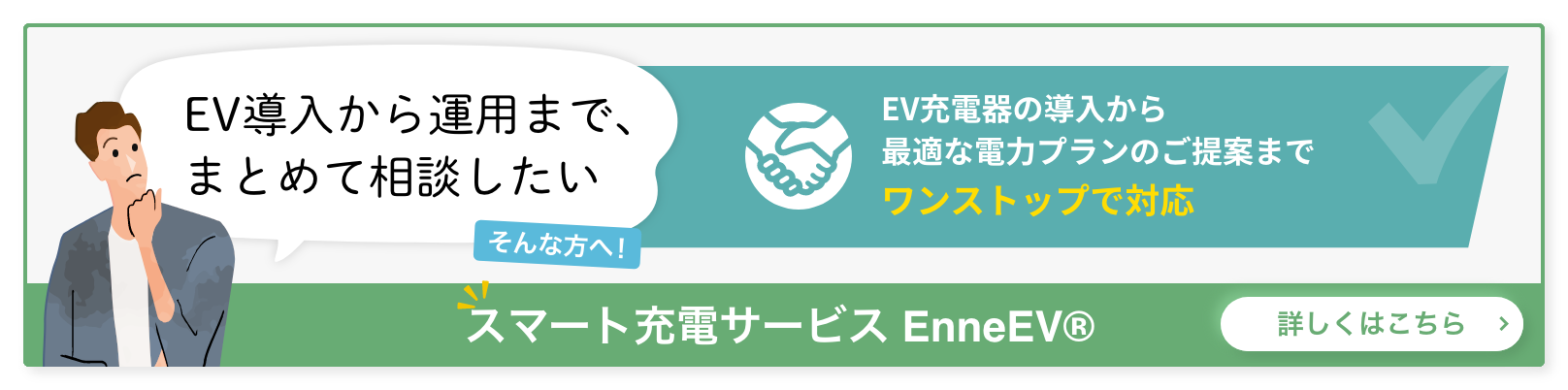脱炭素経営とは?メリット・
デメリットや取り組みを解説

地球温暖化対策が世界的な課題となり、企業にも取り組みが求められている中、脱炭素経営の重要性が増しています。脱炭素経営は環境面だけでなく、企業の競争力強化やコスト削減、人材確保などの面でもメリットがあるため、積極的に採用すべき経営方針です。
本記事では、脱炭素経営の概要やメリット・デメリット、具体的な取り組みを解説します。
目次
脱炭素経営とは
脱炭素経営とは、気候変動対策やその一環である脱炭素の視点を企業経営に組み込むことです。
企業活動により発生する温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにすることを目指します。
従来、企業の気候変動対策はCSR活動の一環として行われることが一般的でしたが、近年では、気候変動対策を自社の経営上の重要課題と捉え、全社を挙げて取り組む企業が増加しています。
具体的には以下のような取り組みが挙げられます。
・省エネルギー化
・再生可能エネルギーの導入
・燃料の転換
・サプライチェーン全体での排出量削減
・環境配慮型製品の開発 など
脱炭素経営が重要視される背景
脱炭素経営が重要視されている背景には以下の要因があります。
・気候変動によるリスクの増大
異常気象の増加、海面上昇、生態系の破壊など、気候変動は人々の生活や経済活動に深刻な影響を及ぼしています。企業活動においても、大規模自然災害によるサプライチェーンの寸断や、事業所・工場の被災といったリスクが増大しています。
・国際的な枠組みの強化
2015年に採択されたパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることが目標として掲げられました。各国はこの目標達成に向けて、温室効果ガス排出削減の取り組みを強化しており、日本政府も2050年までにカーボンニュートラルをめざすことを宣言しています。
こうした国際的な枠組みや国の取り組みを受けて、企業が脱炭素を進める必要性が非常に高まっています。
脱炭素やその実現に向けた課題についてはこちらの記事をご覧ください。

脱炭素経営を行うメリット
脱炭素経営を行うメリットとしては、以下の4つがあります。
競争力の強化
環境意識の高まりにより、取引先や消費者は企業の環境への取り組みを重視するようになっています。脱炭素経営を実践することで、環境配慮型の製品・サービスの開発が促進され、新たなビジネス機会の創出につながります。
また、サプライチェーン全体での取引において、脱炭素への取り組みが取引条件となるケースも増えており、これに対応することで取引機会の維持・拡大が期待できます。
コストの削減
初期投資は必要になるものの、再生可能エネルギーの活用やエネルギー効率の改善により、中長期的な視点で見ればコスト削減が可能となります。
具体的には以下のようなコスト削減方法があります。
・省エネ設備の導入による電力使用量の削減
高効率なLED照明、エネルギー効率の高い空調設備、また最新の生産設備の導入などにより電力使用量を抑えることが可能です。
・生産プロセスの効率化によるエネルギー消費の最適化
IoTやAIを活用した設備の監視・制御、廃熱回収システムの導入、製造工程の自動化などを通じてエネルギー消費を最適化できます。
・将来的な規制の導入に早期対応することによるコスト回避
今後、炭素税や排出量取引などの環境規制が強化される可能性があり、これに早期に対応することで、将来的な負担を軽減できます。
投資家からの評価の向上
脱炭素経営は投資判断の重要な要素となっており、投資家から「環境に配慮した経営を実践している企業」という評価を得ることで資金調達が容易になるケースがあります。
また、脱炭素経営を行う企業向けに政府が用意している補助金や支援制度を活用することも可能です。
優秀な人材の確保
若い世代を中心に環境問題への関心が高まっており、企業選びの際に環境への取り組みを重視する人も少なくありません。脱炭素経営に積極的に取り組むことで多くの人材を惹きつけることができ、優秀な人材の確保につながります。
また、企業として脱炭素という社会的責任を果たすことで、従業員が自社に誇りや愛着を持ちやすくなり、離職率の低下も期待できます。
脱炭素経営を行うデメリット
脱炭素経営には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。
よくあるデメリットの1つはコストの問題です。温室効果ガスの排出量が少ない設備や再生可能エネルギーの導入に初期費用がかかり、これらの設備を継続的に使用するための維持費用も発生します。
また、エネルギーや原材料の使用量の把握、排出量の計測、データ管理など、脱炭素経営を行うにあたり多くの新しい作業が必要となり、これらに慣れるまでに時間がかかることが考えられます。
さらに、脱炭素経営を推進するための専門知識を持つ人材の確保が難しく、既存の従業員の育成にもコストがかかる可能性があります。
このように、設備投資や人材育成などに関して、追加的なコストや一定の工数が発生することには注意が必要です。
脱炭素経営の具体的な取り組み
脱炭素経営の具体的な取り組みとしては、主にSBT、RE100があります。
SBT
SBT(Science Based Targets)は、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標設定の枠組みです。パリ協定に準じた目標が設定されており、Scope 1,2では年4.2%以上の削減、Scope 3では年2.5%以上を目安とした削減※が求められています。
※Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出量
Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出量
Scope3:輸送やフランチャイズなど、Scope 1、Scope 2以外の間接排出量
RE100
RE100は、事業で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことをめざす国際的なイニシアチブです。国際環境NPOのThe Climate Groupにより2014年に発足しました。
遅くとも2050年までに、使用電力の100%を再生可能エネルギーで調達することをめざすことが参加条件となっています。
RE100の詳細についてはこちらをご覧ください。

脱炭素経営の第一歩としてEVを導入しよう
脱炭素経営は、企業が気候変動対策を経営戦略に組み込み、リスクの低減と成長機会の創出を同時に追求する新しい経営手法であり、気候変動に対する問題意識が世界的に高まる中でその重要性は増しています。そのため、今後企業はより積極的に脱炭素経営を実践していくことが求められます。
脱炭素経営の第一歩としては、社用車/公用車のEVシフトが有効な選択肢であり、EVとあわせてスマート充電の仕組みを導入することがおすすめです。
EnneEV(エネーブ)は、EV充電インフラの導入とEV充電器の遠隔制御により、電気料金の上昇を抑制するEVスマート充電サービスです。
最適なEV導入計画のご提案から設備機器の準備、設置工事までワンストップで対応し、充電制御により電気料金を極力抑えた運用が可能となります。これにより、コストを増大させずに企業の脱炭素経営に貢献します。
以下の資料では、EVシフトのメリットやステップをまとめているのでぜひご覧ください。

社用車EV導入 ガイドブック
本資料では、世界と日本のEVシフトの現状やEV導入の際に考慮すべきポイントをわかりやすくご紹介しています。社用車としてのEV導入をご検討されている企業のご担当者様はぜひご覧ください。